前話の復習

ジャージー規則の崩壊 -14話-
前話の復習 ジャージー規則の崩壊 -14話- イギリスはジャージー規則のより、自国の馬を守ろうとしたが、結局は自国の馬を崩壊へと導くことになる。サラブレッドは狭い世界の動物である。 人は強い馬を追い求め、強い馬の遺伝を信...
日本競馬のサラ系 -15話-
サラ系という言葉は、意識をしていないと気が付かないが、サラ(サラブレッド)とは違う。今はほとんどの馬がサラブレッドだが、私が子供のころはサラ系の競争馬が沢山いた。
今思うと、混乱の時代の爪痕が、私の生きた時代にも食い込んでいたいのだと、実感する。サラブレッドは8代連続でサラブレッドと配合されたものはサラブレッドとして認められる。
なので血統書が、サラブレッドの証明になる。血統書の管理もその馬の運命のカギを握る。
日本においては、明治の終わりからヨーロッパからサラブレドが輸入され、1904年(日露戦争)の時には軍馬として、オーストラリアから3,700頭もの馬が輸入された。
しかし、血統書の紛失や、戦争による混乱で、血統が曖昧になってしまった。見た目がサラブレッドであっても、血統書に空白がある限り、サラブレッドとしては認められないのである。
これは、時間が解決するほかなかった。1932年に、日本の初代ダービー馬、「ワカタカ」もサラブレッドではなく、サラ系であったことは有名である。
他にも、アラブ系、アングロアラブ、と言われる競走馬もいたが、今はサラブレッドのみの競馬となった。
「馬」の一言で、まとめられがちな競馬だが、競馬には社会の情勢の影響を受けた歴史があり、その時代を戦い抜いた多くの馬が存在していたことは、覚えていてもいいのではないでしょうか。
少なくとも、現在の競走馬はこの歴史の上に立っているのだから。
このように、イギリスやフランスだけでなく、日本にもいても雑種血統は当たり前にいたのである。
逆に言えば、イギリスがこだわりを持ち続け、サラブレッドを守ってきた事が、いかに重要かつ困難であったかが想像がつく。
やはり、競馬の歴史を作り上げたのはイギリスでると言えるだろう。
ネイティブダンサー -16話-

ネイティヴダンサー -16話-
前話の復習 ネイティヴダンサー -16話- ネイティヴダンサー(1950年誕生)について少し触れておこう。ネイティヴダンサーは後にノーザンダンサーというカナダ産名馬の母父となる。 ノーザンダンサーにつていは後に話をするが...














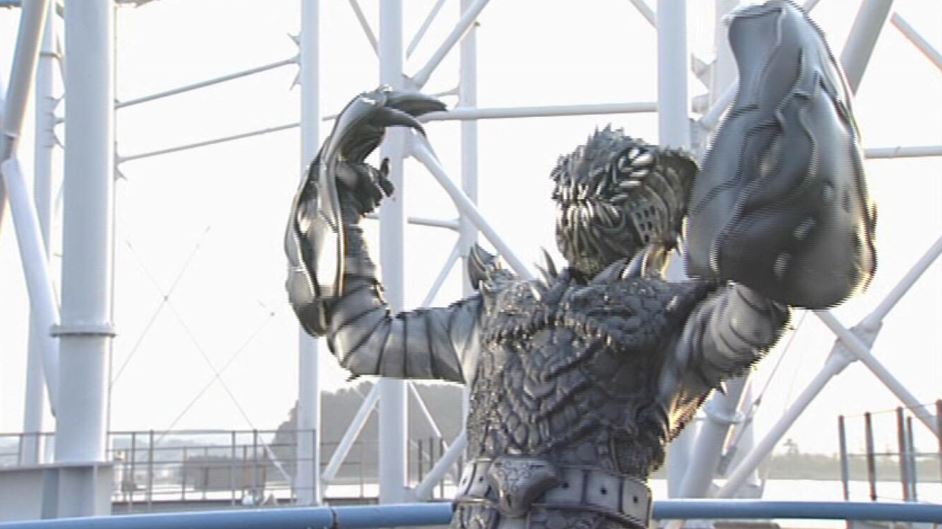



コメント